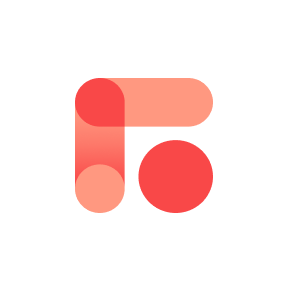近年、求人情報を見ているとフレックスタイムに対応する企業が増加傾向にあると感じます。
以前に比べて、フレックスタイム制度やリモートワークなど従来の勤務形態にこだわらない企業が増え、仕事を探す方にとってもさまざまな選択肢が増えました。
当記事ではフレックスタイム制度について解説します。
働き方の基本や疑問点、注意点を網羅して解説するため仕事探しの基準にお役立てください。
目次
フレックスタイム制度とは?

フレックスタイム制度は一定の期間であらかじめ総労働時間を定め、範囲内で日々の始業・終業時刻や働く時間を労働者自身が自由に決められる制度を指します。
一般的な働き方としては、8時から17時、9時から18時など8時間勤務(休憩を一時間含む)が多いでしょう。しかし、フレックスタイム制度では、一ヶ月の総労働時間を元に日々の就労時間を自身でコントロールする方法が使われます。
そのため、これまで介護や育児で決まった時間の就労が困難だった方々が自分のペースで働けるようになり、時代背景と相まって広がりを見せています。
あわせて知りたい「働き方改革」
フレックスタイム制度とあわせて知りたい用語に働き方改革があります。
働き方改革とは「働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会」を目指すために行う取り組みを指します。
具体的な内容は、年5日の年次有給休暇の取得や不合理な待遇差の禁止、フレックスタイム制の清算期間延長等です。少子高齢化による労働人口の現象や核家族化などさまざまな時代背景が働き方改革を後押ししています。
フレックスタイム制度のメリットは3つ

ここからはフレックスタイム制度を導入するメリットを3つ紹介します。フレックスタイム制度は企業と従業員双方にメリットがあるため、導入を検討しましょう。
働く時間を各自が自由に設定できる
フレックスタイム制度は従業員が働く時間帯を自由に設定できる点が強みです。たとえば、朝早くの出社が苦手な場合、11時から出社し、20時まで働く勤務時間も可能です。また、介護で連続勤務が難しい場合、ケアに要する2時間を中抜けし、その分あとに時間をスライドして勤務もできます。
必ず勤務しなければいけないコアタイムの設定がある場合、従う必要はありますが他の時間を効率的に使える点がフレックスタイム制度最大のメリットです。もちろん、職種によってはフレックスタイム制度の導入が難しい場合もあります。
これまで働けなかった人も働けるようになる
フレックスタイム制度は総労働時間でカウントされるため、毎日一定時間働けない人材に効果的です。これまで介護や育児で働く時間に工夫が必要な方も、両立して働ける可能性があります。たとえば、幼稚園に入る前のお子さんを抱える方がフレックスタイム制度の企業で働く場合、昼間は子どもを見ながらもコアタイムに集中的に働き、朝や夜の空いた時間に残りの数時間分勤務する方法も叶います。
介護や育児で正社員やフルタイム勤務を諦めていた方にとって、フレックスタイム制度は働く機会を与えてくれるでしょう。
働きながらスキルアップしやすくなる
フレックスタイム制度は働きながらスキルアップしたり目標を達成したりする観点からもメリットがあります。
たとえば、ゆくゆく起業するために必要な資格取得の学校に通えたり、7時から15時までの勤務時間を設定し、夜は勉強や交流会などに行きスキルアップしたり、上手な時間の使い方も可能です。
仕事以外に人生プランを持つ方や、今の仕事をベースに企業でステップアップしたいと考える方にとって、フレックスタイム制度を活用することには大きなメリットがあります。
フレックスタイム制度の注意点

フレックスタイム制度は企業と従業員どちらにもメリットをもたらします。しかし、いくつかの注意点を把握してトラブルを防止しましょう。ここではフレックスタイム制度における注意点を3つ紹介します。
コミュニケーションの取り方に工夫が必要
フレックスタイム制度の場合、従業員同士のコミュニケーションに注意が必要です。働く時間がずれるため、今まで気軽にコミュニケーションを取れていた人と細かな点を頻繁に確認できなくなります。その結果、業務に支障をきたす可能性もあります。
フレックスタイム制度のコミュニケーション不足や行き違いを防ぐには、チャットツールやコアタイムの有効活用を徹底する取り組みが大切です。
自己管理能力が問われる
フレックスタイム制度は従業員の自己管理能力が試されます。自己管理が苦手な従業員の場合、時間にルーズになってしまう可能性があります。対策法としては決まった時間に社内ミーティングを実施したり、1時間は同じ業務を担当するチームが一緒に仕事をするなどの取り組みが欠かせません。
また、社内研修としてフレックスタイム制度での働き方を全体で学ぶ機会を設けると良いでしょう。
勤務時間外の連絡がある
フレックスタイム制度は各々が自由に勤務時間を決められる反面、勤務時間外の連絡が発生します。自分にとっては時間外でも他の人は勤務時間である場合、チャットや電話で連絡が入ります。また、クライアントワークが発生する可能性もあるでしょう。
対策法としては部署内で各人の連絡可能時間を共有したり、連絡を頻繁に取る顧客に対して理解を促したりする方法があります。
フレックスタイム制度で働く際の疑問点を解消

ここではフレックスタイム制度を実際に導入する際によくある疑問点を解消します。導入やフレックス制度で勤務をスタートする前に疑問点をなくし、スムーズかつ快適に働きましょう。
どのようなタイムスケジュールで働けばいいかわからない
フレックスタイム制度を導入してすぐは定時勤務での習慣が抜けず、働き方の工夫が難しいでしょう。フレックスタイム制度を導入したにもかかわらず、結局全員が9時から18時で働いているというケースも考えられます。
急に各人が勤務時間をずらすことは難しく感じます。しかし、数ヶ月の時間をかけながらコアタイムを軸に前後を少しずつずらしていき、自分に適した時間を定めましょう。
周りの社員と連絡が取れず業務に支障をきたすのでは?
勤務時間のずれからコミュニケーションや業務に支障をきたすとの意見も見られます。その場合は勤務が定められているコアタイムに連絡やミーティングを入れる他、チャットでこまめに進捗報告を行いましょう。チャットであれば相手が通知をオフにしている時間に送信しても迷惑をかけません。
そのため、急ぎでない連絡はチャットで行い、緊急の場合は電話など社内で規則を作りコミュニケーションの方法を工夫しましょう。
残業はどうなる?
フレックスタイム制度は一定期間の総労働時間でカウントするため、日々の残業時間の扱いに疑問を持ちます。フレックスタイム制は日々の労働時間を自分で決めるため、1日8時間や週40時間の法定労働時間を超えて働いても、すぐに時間外労働にはなりません。
フレックスタイム制では企業ごとに定めた一定の期間を終えた時点で、総労働時間を超えた分を残業代として精算します。
清算期間とは?
フレックスタイム制度は一定の期間(清算期間)の中で残業時間を判断しますが、一定期間を精算期間と言います。なお、精算期間はこれまで1ヶ月でしたが2019年4⽉に労働基準法の改正が行われ、従来の1ヶ月から3ヶ月に延長されました。
まとめ
フレックスタイム制度はさまざまな事情から正社員やフルタイムでの勤務が難しかった方々に効果的な働き方です。導入にはメリットが豊富な反面、注意点も理解しましょう。
企業としては、フレックスタイム制度で働く従業員のサポートが求められます。また、実際に働く従業員側も自身で定めた時間で効率的にコミュニケーションをとったり業務を進める力が求められます。フレックスタイム制度をうまく活用し、ライフワークバランスの向上に努めましょう。
フレックスタイム制度の企業への転職を検討する場合は「gigbase」への登録がおすすめです。
今までの経験やスキルを元にフレックスタイム制度をはじめとしたさまざまな働き方を提供する企業との出会いの機会を支援します。
気になる方はぜひ「gigbase」に登録して求人を検索してみてくださいね!